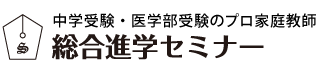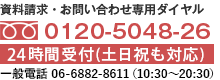2025年の中学入試から、今回は大阪星光学院中について振り返ります。今年度の受験データを細かく分析、各科目の傾向やポイント、2026年の対策等について徹底解説いたします!
CONTENTS:
1.2025年度、大阪星光学院中入試の特徴
大阪星光学院中の入試は、出願時にI型(国語・算数・理科・社会の4科目型)、またはⅡ型(国語・算数・理科の3科目型)のどちらかを選ぶことができます。
試験時間と配点は、国語と算数が各60分で120点、理科と社会は各40分80点の合計400点満点で、判定はI型、Ⅱ型それぞれ以下の通りです。
<I型(4科目型)> 評価点=下記のうち最も高得点の点数
・国語・算数・理科・社会の合計点
・国語・算数・理科の合計点×1.25
・国語・算数・社会の合計点×1.25
<Ⅱ型(3科目型)> 評価点
・国語・算数・理科の合計点×1.25
合格判定にI型、Ⅱ型の区別は行っていません。当然のことですが、最高点が3パターンから評価される4科目のI型受験の方が有利と考えられるでしょう。大阪星光学院中を第一志望に考えるのなら、やはりI型の4科目受験のほうがいいでしょう。
実際に、今年も受験者数698名のうち、I型受験者が500名、Ⅱ型受験者が198名と71.6%がI型で受験しています。例年I型受験者は75%くらいです。
2.2025年の入試データ
※( )内は昨年比 <人>
|
【募集人員】 190名 |
志願者数 |
受験者数 |
合格者数 |
実質倍率 |
|
I型(4科受験) |
525(+7) |
500(+5) |
216(-12) |
2.31(+0.14) |
|
Ⅱ型(3科受験) |
228(+39) |
198(+32) |
67(-5) |
2.96(+0.65) |
|
合 計 |
753(+46) |
698(+37) |
283(-17) |
2.47(+0.27) |
190名の募集に対し志願者数は753名、受験者数は698名でした。昨年は志願者数、受験者数ともに30名以上減少しましたが、今年は2023年よりも増え、大幅な増加となりました。
逆に合格者数は大きく減少し、実質倍率は昨年より上がって2.47倍となりましたが、大阪星光学院中の実質倍率は例年2.5倍前後なので、概ね例年並みといえるでしょう。
3.大阪星光学院中志願者の受験日程パターン
大阪星光学院中志願者の受験日程パターンを表したものが下記の表です。
|
前受け校 |
・愛光(愛媛) ・岡山白陵(岡山) ・北嶺(北海道) |
|
|
1日目 1/18(土) |
2日目 1/19(日) |
3日目 1/20(月) |
|
<午前> ・大阪星光(大阪)
<午後> ・清風(大阪) ・明星(大阪) ・帝塚山(奈良) |
<午前> ・清風南海(大阪) ・須磨学園(兵庫) ・明星(大阪) ・帝塚山(奈良) <午後> ・西大和学園(奈良) ・高槻(大阪) ・須磨学園(兵庫) |
・東大寺学園(奈良) ・洛南高附(京都) ・清風(大阪) ・帝塚山(奈良)
|
|
4日目以降(1/21~) |
・清風南海(大阪) ・六甲学院(兵庫) ・洛星(京都) ・白陵(兵庫) ・清風(大阪) |
|
大阪星光学院中志願者の受験日程パターンは、統一受験日前の前受けとして、愛光、岡山白陵、北嶺などを受験し、一つ合格を確保の上、統一受験日初日の午前に行われる本命、大阪星光学院中を受験するのが理想的です。
大阪星光学院中の入試は初日午前の試験1回だけですので、併願パターンとしては地域などを含め、さまざまな選択が考えられます。他の最難関中学にチャレンジすることもできますし、手堅くランクを下げた併願も可能です。
大阪星光学院中の入試は、3科受験なら12時30分頃、4科受験でも14時頃には終わります。同日に2校受験するのであれば、そこから移動し清風、明星、帝塚山などを受験することも可能です。
2日目は、午前中に清風南海、須磨学園、明星、帝塚山などを受験、午後は西大和や高槻、須磨学園などが考えられます。
2日目の午後に大阪星光学院中の合格発表がありますので、合格していればここで終了です。そうでなかった場合は、3日目に東大寺学園や洛南高附にチャレンジするか清風、帝塚山などとなるでしょう。
4日目以降は清風南海、六甲学院、洛星、白陵、清風などを受験したパターンが多かったようです。
4.大手塾別合格者数
関西大手進学塾の大阪星光学院中合格者数は多い順に下記のようになりました。
※( )内は前年比 (人)
|
浜学園 |
能開センター |
馬渕教室 |
希学園 |
|
105(+4) |
59(-13) |
51(-2) |
39(±0) |
|
日能研 |
進学館 |
SAPIX |
第一ゼミナール |
|
24(-10) |
9(+3) |
9(+6) |
5(+4) |
3年連続で100名以上の合格者を出した浜学園が、今年はさらに他塾を大きく引き離して安定した実績を上げています。大阪星光学院中に強い能開センターも、一昨年合格者数が大きく減少し昨年は少し増加に転じましたが、今年はまた10名以上の減少となりました。
今年は大阪星光学院中の合格者数が昨年より17名も減っているので、どの塾も合格実績を上げるのは難しかったと思います。そのような中で昨年と同じ合格者数を出した希学園や2名減少に抑えた馬渕教室は検討しているといえるでしょう。
5.科目別成績データ
大阪星光学院中2025年合格者の各教科の平均点と受験者平均点との差、合格者最高点と最低点を表したものが下記の表です。
(前年比)<点>
|
科 目 |
受験者平均 |
合格者平均 |
合格者平均との差 |
合格者最高点 |
合格者最低点 |
|
国 語 |
77.5(+6.9) |
83.7(+7.8) |
6.2(+0.9) |
108(+5) |
57(+12) |
|
算 数 |
54.3(-11.7) |
69.3.(-10.0) |
15.0(+1.7) |
120(+5) |
37(-4) |
|
理 科 |
53.1(-3.4) |
59.4(-2.2) |
6.3(+1.2) |
80(+2) |
38(-5) |
|
社 会 |
57.0(+5.4) |
61.2(+5.4) |
4.2(±0) |
79(+5) |
29(+3) |
|
総 合 |
240.3(-6.1) |
273.7(-1.7) |
33.4(+4.4) |
365.0(+31.25) |
250.0(-2.5) |
(※国語、算数は各120点、理科、社会は各80点の400点満点)
大阪星光学院中の2025年度入試は、昨年より難化しました。2023年の試験が過去10年でもっと難度が高く、2024年も過去10年で2023年に次ぐ2番目に高い難度の試験でした。高難度の試験が2年連続して続いたので、今年は反動で易しくなると思われていましたが、予想に反し、2023年よりさらに難化しました。
特に算数が大きく難化し、受験者平均点の得点率は45.3%と5割を大きく割り込み、合格者平均点の得点率でも57.8%と6割にも届きませんでした。
今年はとても特徴的な試験結果となりました。受験者平均点が大きく下がったのに対し、合格者平均点はあまり下がっておらず、また合格者最高点は大きく上がりましたが、合格者最低点は下がっています。
つまり、上位から下位までの差が広がっているように見えます。算数もここまで難度が高くなると受験者平均点と合格者平均点の差は縮まるのですが、逆に差が広がっているのもその表れです。
6.2025年度入試からみる科目別の傾向と対策
今年度の大阪星光学院中入試を参考に、教科ごとの傾向と対策をご紹介します!
◆国語
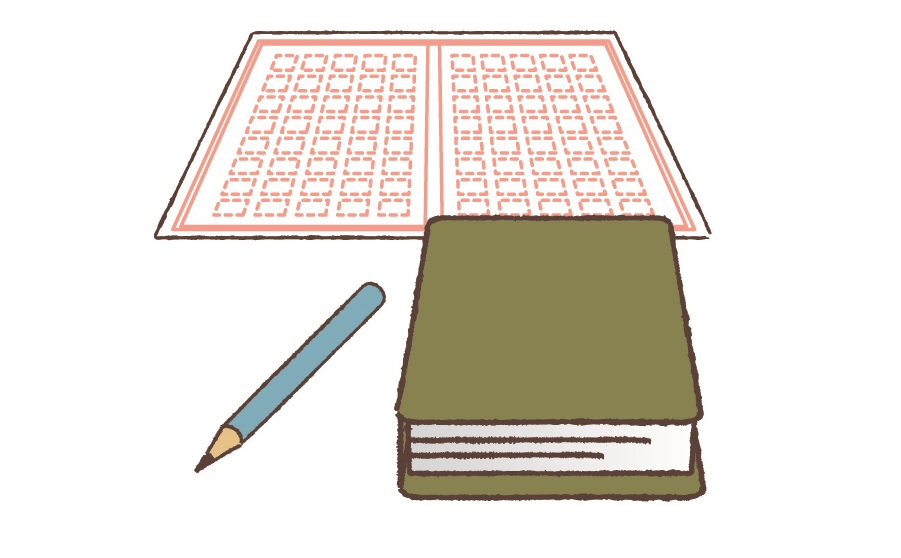
【試験時間・配点と構成】
60分120点満点の大問3題構成の試験で例年通りでした。大問1と大問2は長文読解問題、大問3が知識問題です。大問1と2の長文読解は、例年物語文と論説文で、今年の大問3の知識問題は、傍線部の言葉を別の熟語に変換する(カタカナで書かれた語群から適切な語を選び漢字で解答する)問題でした。
【難易度】
大阪星光学院中2025年国語試験は、過去10年でも受験者平均点が最も高く、77.5点(得点率64.6%)でした。
大問1~2の小問で出題される漢字も、今年は大阪星光学院中受験生にとっては平易な問題だったと思われます。例年は物語文でやや難解な記述問題がありますが、今年はそれも取り組みやすい内容でした。
【傾向と対策】
大問1と2は小問が各6題ずつで、問題数は多くありませんが、問題用紙7枚と多くの文字数を読まされることになりますので、読書スピードと読解力が必要です。
今年もそうですが、大阪星光学院中の漢字も含めた知識問題は、他の最難関校に比べさほど難易度が高くないのに加え、例年全体の1/4くらいの配点で出題されています。大問3の知識問題は、年度により出題単元はさまざまですが、慣用句からの出題が比較的多くなっています。
記述解答は字数指定のある記述が各大問中に2問ずつあり、60字~100字の長文を書きます。問題数自体は少ないものの、配点が大きいので記述対策もしっかり行っておきましょう。
知識問題はしっかりと得点源にし、記述解答は満点でなくても確実に部分点がもらえるような解答ができるようにしておきたいところです。
今年の大阪星光学院中の国語は難度が低かったので、来年は少なくとも今年度に比べると難化すると思われます。2023年や2018年のような難度の高かった過去問にも取り組んでおきましょう。
◆算数
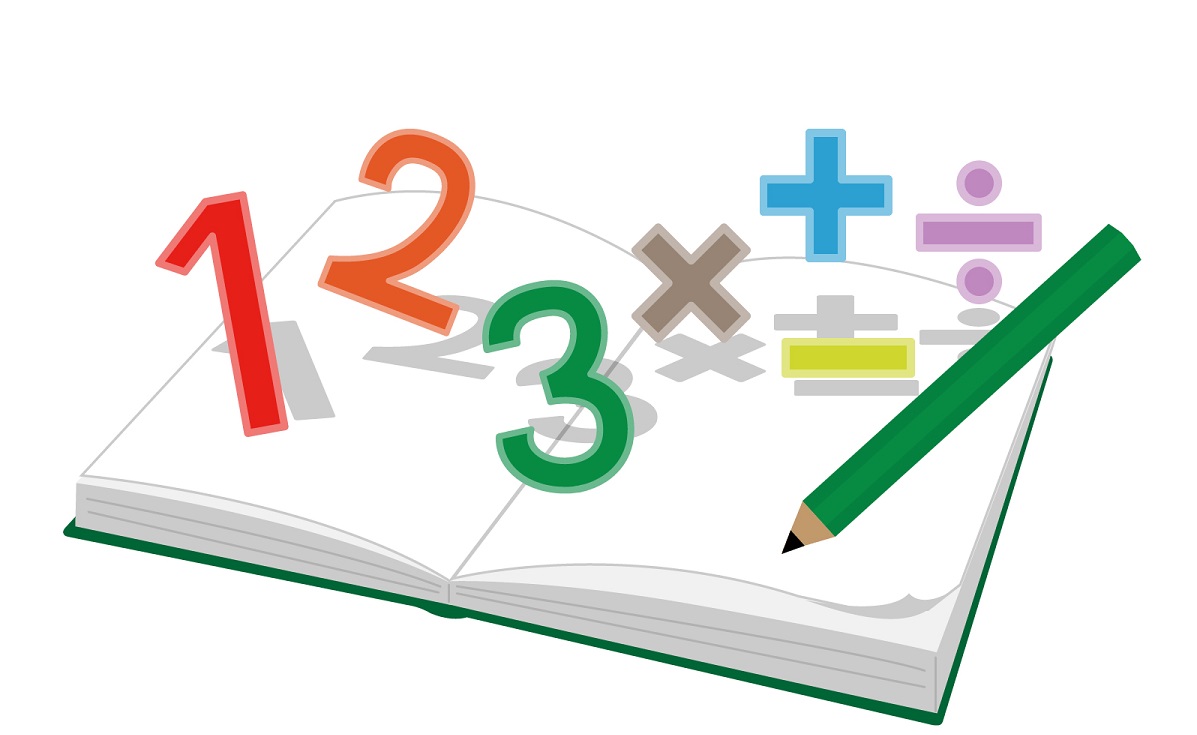
【試験時間・配点と構成】
60分120点満点の試験で、今年も例年通り大問5題構成でした。問題用紙も例年通りB4用紙3枚で、解答もすべて問題用紙内の解答欄に書き込む形式です。途中で1題だけ解き方を書かせる問題が出されているのも例年通りでした。
【難易度】
大阪星光学院2025年算数入試は、大きく難化し2022年度よりも受験者平均点が下がり54.3点(得点率45.3%)と、過去15年で最も難度の高い試験となりました。
ちなみに、2022年度入試が受験者平均点58.1点(得点率48.4%)で、やはりたいへん難しい試験でしたが、2023年、2024年と易化が続き例年並みの難易度になっていました。今年は再び大きく難化となりました。
【傾向と対策】
大問5題構成の大問1は小問集合5題で、小問1は計算問題、残り4題のうち2題は図形単元の出題というパターンが多く、今年度も小問4は立体図形、小問5は平面図形の問題でした。
大問1の小問集合は例年比較的解きやすく、時間をかけずに解き進めなければならないのが基本ですが、今年度は小問4と5がやや難しく時間がかかったり、後回しにしたりした受験生も多かったのではないかと思われます。
大問2~5では、平面図形、立体図形、速さの単元からの出題が多く、大問1の小問でも図形問題が出題されるので、大阪星光学院中を志望するのなら図形に苦手意識があると合格を勝ち取るのが厳しくなるでしょう。しっかりとした図形対策が必須となります。
入学試験では、解き進める順番や問題の取捨選択の判断も合否を分けるポイントになります。今年のように難度の高い試験では、大問5の立体図形の切断の問題の後半は捨て問にしてもいいレベルの問題でしたが、どの問題を解いてどの問題を捨て問にしていいのかは、多くの問題を演習しなければ判断できません。
大阪星光学院の大問1には、各小問に「計算欄」がついています。答えが正しければ問題ないのですが、答えが間違っている場合は計算欄の途中式を見て考慮され、加点される可能性があります。
基本的に答えだけの解答形式ですので、答えが正しければ計算欄は見られないと考えていいでしょう。ただし、後半の大問の〈求め方〉を書く問題については、答えが間違っていても途中式を見て部分点がもらえるのはもちろんですが、たとえ答えが正しくても求め方で正しくなければ減点対象にもなります。
大阪星光学院中の算数は、大問2以降は1問を除きすべて解答のみを書く形式です。解き方が正しくても最後に計算ミスや転記ミスなどのケアレスミスをしてしまうと1点にもなりません。ケアレスミスをしないように普段から意識して取り組みましょう。
※ケアレスミスの対処法については下記のブログの「3.算数でよくあるケアレスミスとその対処法」で詳しくご紹介していますのでご参照ください。
↓↓
『得点アップにつながる答案用紙の書き方!ケアレスミスをしやすいタイプと対処法』
◆理科

【試験時間・配点と構成】
40分80点満点の試験で、今年の問題用紙はB4用紙7枚に解答用紙が別途1枚の計8枚となり、昨年より問題用紙が1枚増えました。
出題分野は、今年も物理・化学・生物・地学の各分野から1題ずつの大問4題構成で小問数は40問前後、出題順も地学→化学→生物→物理で例年通りでした。
【難易度】
大阪星光学院中2025年理科入試は、やや難度の高い試験でした。2024年は例年並みの難易度でしたが、今年は昨年よりも合格者平均点が2.2点下がり、例年と比較してもやや難度が高く難しい試験となりました。
問題用紙が1枚増え、多くの字数を読まされることになったことも、平均点が下がった一因かと思われます。科目は理科ですが、スピードと読解力も求められる試験です。
【傾向と対策】
大阪星光学院中の理科は、物理、化学、生物、地学分野がほぼ均等に出題されるので、苦手分野を作らないように学習する必要があります。
昨年は知識問題がやや多く出題されていましたが、今年は小問40問において知識問題、計算問題、思考問題がほぼ均等に出題されていました。
今年の物理分野は、2023年と同じ「電熱線」の問題でしたが、この分野は力学の出題が多く、特に「ばね」が多い傾向にあります。計算問題も多いのですが、他の最難関校に比べて煩雑な計算はありません。
化学分野は溶解度や中和などの計算問題が頻出です。生物分野は実験をもとにした思考問題が多く、問題文が長くなる傾向があります。難問ではありませんが、しっかりと読む必要があります。
地学分野は各単元まんべんなく出題されるイメージですが、2020年以降、星座や月、太陽といった天体からの出題がありません。もしかしたら来年くらいに天体からの出題もあるかもしれません。各単元とも省かず目を通しておかなければなりません。
前述のように、出題順は分野別に地学、化学、生物、物理の順ですが、例年物理はやや難度が高めな計算問題が出題されています。大問4の物理分野にしっかり時間が取れるように大問1~3で時間をかけすぎないよう、時間を計って過去問演習をしておくようにしましょう。
◆社会

【試験時間・配点と構成】
40分80点満点の試験で、今年は問題用紙がB4用紙9枚と解答用紙が1枚の10枚でした。昨年よりも問題用紙が1枚減りましたが、かなり多くの文字数を読むことになります。
今年もそうですが、例年大問2題構成で、地理分野と歴史分野中心の総合問題にそれぞれ分かれています。
公民分野は各小問の中に組み込まれて出題されますが、問題数的には地理や歴史分野と比べて多くはありません。出題割合は、概ね歴史と地理分野がそれぞれ全体の40%強で、公民分野が10%強といったイメージです。
今年は例年になく公民分野の出題割合がやや高かったのですが、それでも全体の2割ほどでした。
【難易度】
大阪星光学院中の2025年社会科入試は、ほぼ例年並みの難易度でした。2024年、2023年と2年連続でやや難度の高い試験でしたので、今年は易化して例年並みの難易度となりました。
大阪星光学院中社会の受験者平均点は、例年60点弱程度なので、今年の平均点57.0点も概ね例年並みといえるでしょう。
【傾向と対策】
今年も問題用紙が9枚もありボリュームがあるように感じますが、図や写真、グラフ、表などが用紙の半分くらいを占めていることもあり、思ったほど文章量は多くありません。それでも試験時間が40分と短いので、スピーディーに読み進めなければ時間が足りなくなります。
今年もそうですが、例年正誤選択問題も多く出題され、問題によって「正しいものを選びなさい」と「誤っているものを選びなさい」という両方の指示が混在しています。問題文を読みながら指示部分に線を引くなど、ケアレスミスをしないよう注意しましょう。
大阪星光学院中では、たとえ「漢字で書きなさい」という指示がなかったとしても検定教科書に漢字で書かれている語句や人名などは漢字で答えられなければ減点となります。当然ですが誤字は×になりますので、きれいに正確に書けるようにしておきましょう。
7.まとめ~大阪星光学院中合格への道~
.jpg)
大阪府内最難関男子校として人気のある大阪星光学院。例年、実質倍率は2.5倍前後で毎年多くの男子生徒が受験し、今年は受験者数が大きく増えました。学校は大阪市内のほぼ中央に位置し、駅からも近く通いやすいことも人気の一つです。
学校は都会の中にありますが、和歌山や長野に研修施設を持ち、自然に触れながらの勉強合宿など、さまざまな学校行事があることも魅力です。毎年東京大学や京都大学、医学部など最難関大学へ進学する卒業生を多く輩出しています。
総合進学セミナーには大阪星光学院中に特化して指導できる講師も多く在籍しています。毎年のように大阪星光学院中志望の受験生を指導しているため、入試傾向にも精通しています。お子さま1人ひとりの現状を踏まえ、入試までの限られた時間を無駄のない効率的な指導で合格を目指します。
大阪星光学院中受験はもちろん、併願校の選定など、中学受験に関するさまざまなお悩みなどがありましたら、お気軽にご相談ください。

大阪星光学院中対策ならお任せください!
保護者の方の疑問にお答えし、不安を解消する