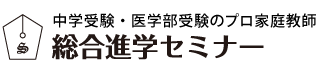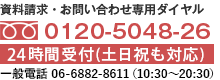朝すっきりと目覚めることが出来ていますか?
大人であれば、寝たはずなのにだるい、疲れている、ぼーっとして動くまでに時間がかかるといった経験がある方も多いと思います。
同様に子供においても、だるい、起き上がるのに時間がかかるといった、朝すっきり起きることが出来ない不調が小学校の高学年あたりから増えてきます。
このような不調は、日頃の食事による栄養素の供給が、成長に必要な需要と見合わなくなった際にも特に強くみられ始めます。
また、朝の調子は睡眠に大きく左右され、睡眠時間の問題だけでなく、睡眠の質が深く関係しており、この睡眠の質にも食事が影響を与えています。
受験生にとっては、本番の試験は午前中から行われることが多いため、朝の目覚めから良いコンディションで活動を始めることは非常に重要になってきます。
そこで今回は、機嫌よくすっきりとした朝を迎えるための食事についてご紹介します。

◉朝の不調は身体からのSOS⁈
日中は元気に活動できるのに、朝起きるのがつらい、しんどいといった経験をしている受験生も多いと思います。
夜遅くまで勉強しているから、朝は低血圧だからこれが普通といってやり過ごしているかもしれません。
しかし、実はこれらは成長に伴う体内での栄養不足からくるSOSであることも多いのです。
特に、高学年以降の女子においては月経開始に伴う鉄の不足に比例するように不調も深刻度を増していきます。
また、性別に関係なくタンパク質やビタミンB群といったどの年代においても、多くの量が必要とされ不足しがちな栄養素の不足が朝に不調として強くでてくることもあります。
子供の成長に伴い、食事量だけでなくその内容の見直し、強化したい栄養素や食材をはっきりと意識していくことが重要になってきます。
鉄を多く含む食材……レバー、牛肉、カツオ、マグロ、あさり、卵 など
ビタミンB群を多く含む食材……豚肉、鶏肉、赤身魚、魚介類、青菜、納豆 など
タンパク質を多く含む食材……肉、魚、卵、大豆製品、練り物 など
特に、タンパク質においては意識して食べているはずなのに不足していることがよくあります。
毎食主菜をつける事だけでなく、副菜や間食からも摂取をしていく意識が必要です。
<レシピ>
~牛こまカルビのチーズボール~
【材料】(6個分)
- ・牛肉こま切れ……140g
- ・シュレッドチーズ……12g
- ▼▼▼ A ▼▼▼
- ・砂糖……小さじ1
- ・しょうゆ……小さじ1
- ・オイスターソース……小さじ1/2
- ・おろしにんにく……1/2片分
- ▲▲▲ A ▲▲▲
- ・片栗粉……適量
- ・マヨネーズ……適量
- ・青のり……適量

【作り方】
- ① 牛肉こま切れは包丁で粗みじん切りにし、ボウルにAといっしょに入れてよくこね合わせる。
- ② シュレッドチーズを6等分にして丸める。
- ③ ①の牛肉も6等分にして、中央に➁のチーズを包み込んで丸める。
- ④ ③の表面に片栗粉をまぶして、油をひいたフライパンに入れ中~弱火で蓋をして片面3分程ずつ焼く。
- ⑤ 最後に上にマヨネーズを少しのせ、青のりをふったら出来上がり。

鉄分とタンパク質が豊富な牛肉に、ビタミンB2やタンパク質を含むチーズを合わせて食欲をそそるおかずにしました。
お弁当やごはんのおかずはもちろん、ついつい食べたくなる味とサイズで小腹がすいた時のタンパク質たっぷりの間食としてもおすすめです。
牛肉の代わりに豚肉を使って作ると、タンパク質とビタミンB群豊富な一品にもなります。
作って冷凍もできるので、是非多めに作ってさまざまなシーンで食べてみて下さい。
◉睡眠の質が目覚めを決める
よく寝たはずなのに疲れが取れない、だるいといった経験はありませんか?
前日の疲れを引きずっていることもありますが、慢性的にこのような感覚に陥っている場合は、眠っている間に疲れている可能性もあります。
本来、睡眠中は身体の機能も休息をとり回復をしているのですが、睡眠中に体の機能が働かざるを得ない状況を前日の食事などによって作ってしまっていることがあります。
このような食事が続くと、朝の慢性的な疲労感が強く続き、1日の活動にも悪影響を及ぼしてくる悪循環に陥っていきます。
反対に、睡眠時間は長くなくてもすっきり目覚められ、朝から元気に活動できる人もいます。
これは、短時間であっても質の高い睡眠により体も脳も十分に回復できており、それにはやはり睡眠の質をあげる栄養素が関係してきます。
◆睡眠を妨げる食事
《糖質》
良くも悪くも睡眠の質に大きな影響を与えるのが「糖質」です。
寝る前の夕食などで多くの糖質を摂ると、就寝中に急激に血糖値が上がり、その後上がった分急激に血糖値を下げようとインスリンというホルモンが大量に分泌されます。
すると今度は、下がった血糖値を上げようとアドレナリンなどのまた別のホルモンが分泌される過程で、歯ぎしり、寝汗、中途覚醒、悪夢、翌朝の疲労、寝起きが悪い、寝つきが悪いといったさまざまな症状が出てきます。
これを防ぐためには、夕方以降から就寝前にかけての間食や食事における、糖質の摂り方の以下のポイントが重要になってきます。
・糖質の量とタイミング
好きな糖質は午前中に食べるようにし、午後からは糖質控えめおかず多めを意識する。
・糖質単体で摂ることは控える
お菓子、ジュースはもちろんのこと麺類、丼、おにぎりだけといった糖質単体の食事は血 糖を急激に上げる要因になるため注意する。
・食べる順番
副菜or主菜→主食の順に食べることで、血糖値の上がり方も緩やかになる。
その他、夕食は就寝前の2~3時間前に食べ終えるなどの意識も重要になってきます。
《空腹》
就寝中に食事による血糖が低下してくると、アドレナリンなどのホルモンが分泌され肝臓や筋肉に蓄えられた糖がエネルギーとして取り出され、血糖を維持します。
空腹のまま就寝すると体内では低血糖状態になる時間が増え、その分血糖を上げるためのホルモンが多く分泌されます。
それに伴い、自律神経の交感神経が興奮し、体は興奮状態(戦闘モード)となるため、疲労回復するどころか緊張で深い眠りにつくことができず、場合によっては中途覚醒することもあり、朝起きると疲労感が増したような状態に陥ってしまいます。
そのため、就寝前に空腹を感じた場合我慢するのではなく、次に紹介する良い睡眠を助ける栄養素を含む食材を適量摂取することが重要です。
◆良い睡眠を助ける栄養素
《神経伝達物質の主原料となるタンパク質》
私たちは脳内で神経伝達物質というものが作られ作用することで、リラックスしたり、やる気が出たり、不安になったり、幸せな気分になったりとメンタル状態が変化していきます。
この神経伝達物質は睡眠にも大きく関わっており、特にGABAと呼ばれる伝達物質には脳の興奮を抑えて睡眠の質を安定させる働きがあります。
また、メラトニンという神経伝達物質は、体を睡眠モードに切り替えスムーズに眠りに入るために重要な役割を果たしています。
どちらも、タンパク質の構成物質であるアミノ酸を原料として作られるため、就寝前から十分にタンパク質を摂取し、体内をアミノ酸で満たしておくことが重要になってきます。
《脳内伝達物質の合成に必須の栄養素》
脳内伝達物質はタンパク質が主原料となりますが、それだけでは作り出すことが出来ません。
そこには、合成反応を起こすためのその他の栄養素が必須となってきます。
それが、マグネシウム、ビタミンB群、鉄といった栄養素になります。
特に、マグネシウムはメラトニンを作り出す際に必須となり、マグネシウムの摂取量が上がると睡眠の質が上がることや、適量摂取で睡眠時間が適正になることも報告されています。
そして、ビタミンB群と、鉄は多くの脳内伝達物質の補酵素としてその必要量も多くなります。
マグネシウムを多く含む食材……魚、大豆製品、ナッツ類、にがり など
<レシピ>
~茹で干し大根のカレーツナサラダ~
【材料】(4~6人分)
- ・茹で干し大根……40g
- *なければ、切り干し大根でも可
- ▼▼▼ A ▼▼▼
- ・ツナ缶(オイルあり)……1缶(70g)
- ・カレー粉……小さじ1
- ・マヨネーズ……大さじ1
- ・しょうゆ……小さじ1
- ・顆粒コンソメ……小さじ1
- ▲▲▲ A ▲▲▲
- ・塩……1つまみ

【作り方】
- ① 茹で干し大根は、流水で洗って水に10分ほどつけて戻し、水気を絞る。
- ② ボウルにAと茹で干し大根を入れてよく混ぜ合わせる。
- ③ 最後に、塩で味を調えたら出来上がり。

天日で干した大根は旨味が増すだけでなく、ビタミンBや鉄、マグネシウムなどのミネラルの量が何倍にも増して凝縮されます。
ここに、タンパク質たっぷりのツナ缶を加えてカレー風味にすることで、とても食べやすくなります。
お弁当や作り置きの副菜にも便利です。