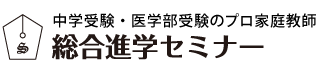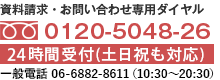この時期、挑戦を終えた受験生の大きな成長を感じられているご家族も多いと思います。
一方で、新たな受験生たちがこれから自分が決めた目標に向かい走りだそうとしている中で、伴走していくご家族には、是非「食事」を通しての見守りとサポートをして頂きたいと思います。
というのも、受験に向けて多くの努力を重ね、より良いパフォーマンスを発揮するために欠かせないのが、食事による土台作りであるからです。
これまで、脳を働かせるには?集中力を高めるには?体調を崩さないためには?
といったさまざまな観点から、どのような栄養素や食事をどのように摂るのが良いかといった事を紹介してきました。
しかし、これらの栄養素や食事の摂り方を実践する前に準備しておかなければいけないことがあります。
それは、摂取した栄養素を体内で効率よく使うために、食べた物を消化・吸収する能力を高めることです。
この消化吸収の機能を高めるためにも、「食事」が重要になってきます。
そこで今回は、何を食べるかの前に、食べた物をきちんと自分のものにするための食事についてご紹介します。

◉消化はタンパク質でできている
食物は口に入ると、胃や腸を通って消化酵素の働きにより消化されやすい状態へと分解された後、小腸から吸収されます。
消化酵素には、口から出る唾液や胃から出る胃酸、腸で分泌される胆汁などがありますが、いずれも体の臓器や細胞同様にタンパク質が主材料となり作られています。
そのため、タンパク質の摂取不足が続くと、消化酵素を分泌する臓器の機能が落ちるだけでなく、消化酵素自体もうまく作られない状況になります。
その結果、消化・吸収能力が落ち、たくさんお肉を食べられない、すぐに胃もたれをする、油脂が多い物で消化不良を起こしがちといった悪循環に陥りやすくなります。
加齢に伴い消化・吸収能力は落ちるのですが、近年では若い人や子供であっても「肉が苦手」、「少し脂っこいものを食べるとお腹がゆるくなる」といった人も増えています。
まずは、食べられるタンパク質から毎食しっかり取り入れていくことが、消化能力を上げるうえで重要になってきます。
消化能力が落ち一度に多くのタンパク質が食べられない場合などは、プロテインやアミノ酸といったすでに分解され、消化吸収しやすい形のものを摂ることも必要です。
摂取目安量は、大人であれば体重1kg につき1~1.5g 程度のタンパク質が必要といわれますが、成長期の子供であればさらに必要量は多くなります。
《食物に含まれるタンパク質量》
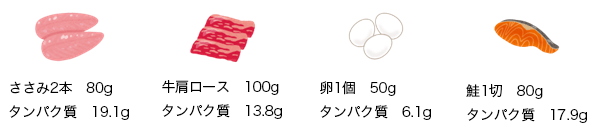
◉タンパク質代謝に欠かせないビタミンB群
消化吸収能力を上げるにはタンパク質の摂取が重要であると上記しましたが、タンパク質だけを食べていてもそれらは体内でうまく機能しません。
食べたタンパク質を体内で代謝させ、エネルギーや消化酵素などのあらゆる細胞に作り変えるためには、その代謝を回すためのビタミンやミネラルの存在が欠かせません。
その代表的な物がビタミンB群であり、その中でもビタミンB6はタンパク質を構成するアミノ酸の分解と再合成の両方において必要であり、その必要量もタンパク質摂取量に伴い増やしていかなければなりません。
◆ビタミンB6を多く含む食材……豚ヒレ肉、レバー、赤身魚、パプリカ など
タンパク質とビタミンB群を意識できたら、次はそれらを食べるタイミングを工夫することで、さらに摂取効率が上がります。
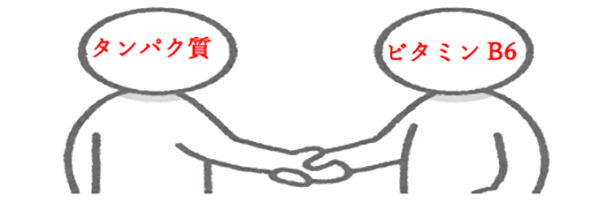
<レシピ>
~豚肉とほうれん草のオイバタ炒め~
【材料】(3~4人分)
- ・豚ヒレ肉……130g
- ▼▼▼ A ▼▼▼
- ・酒……大さじ1
- ・塩……2つまみ
- ▲▲▲ A ▲▲▲
- ・片栗粉……適量
- ・ほうれん草……3束
- ・卵……2個
- ・長ネギ……1/2本
- ・にんにく……1片
- ・バター……10g
- ・オイスターソース……大さじ2/3

【作り方】
- ① ほうれん草はよく洗って、食べやすい長さに切る。
長ネギは斜め切りにし、にんにくはみじん切りにする。 - ② 豚肉は繊維に逆らうようにして食べやすい大きさに薄切りにし、Aを加えて軽く揉みこんだら、片栗粉をまぶして沸騰したお湯で、一枚ずつ火が通るまで茹でてざるにあげる。
- ③ 卵に塩を一つまみ(分量外)加えて溶きほぐし、油をひいたフライパンで半熟状態に炒めたら別皿に移しておく。
- ④ フライパンにバターを溶かして、にんにくと長ネギ、ほうれん草の茎の方を入れて炒める。
- ⑤ 全体に火が通ってきたら、ほうれん草の葉を加えて炒めしんなりしてきたら、➁の豚肉とオイスターソースを加えてさらに炒める。
- ⑥ 最後に火を止めて、③の卵を戻して全体に味を行きわたらせたら出来上がり。

タンパク質とビタミンB群豊富な豚肉と卵に合わせたほうれん草は、鉄やカリウム、ビタミンCなどタンパク質の代謝に欠かせない栄養素をたくさん含んでいます。
豚肉を茹でたり、卵を別に炒めておいたりすることにより、それぞれが硬くなり過ぎずに冷めても美味しい炒め物になりますので、お弁当などにもおすすめです。
◉タンパク質の消化・吸収が上がるタイミング
私たちの身体は体内で過剰なものがあれば排泄しようとし、反対に不足すると積極的に吸収しようとさまざまな機能を働かせます。
そのため、タンパク質も体内で少なくなるタイミングに食べ物から摂取することで、それらをうまく吸収することが出来ます。
そもそもタンパク質は体内では筋肉中に多く存在するため、トレーニングなどの運動により筋肉中のタンパク質の分解が進むと、その直後に入ってくるタンパク質は体内で吸収されやすくなります。
(トレーニング直後にプロテインを飲むのもそのためです。)
日常生活の中では、何時間も絶食状態が続く就寝中にエネルギーを維持するためにタンパク質の分解が進むため、起床後すぐに肉や魚、卵などの食品を摂るとタンパク質をうまく吸収しやすくなります。
朝食には、是非主菜をしっかり取り入れてみてください。
<レシピ>
~肉団子のれんこん中華スープ~
【材料】(4人分)
- ・鶏ももひき肉……200g
- ▼▼▼ A ▼▼▼
- ・片栗粉……大さじ1
- ・塩……小さじ1/4
- ▲▲▲ A ▲▲▲
- ・れんこん……100g
- ・長ネギ……1/2本
- ・しょうが……1片
- ・水……300ml
- ・豆乳……200ml
- ・ごま油……大さじ1
- ▼▼▼ B ▼▼▼
- ・顆粒鶏ガラスープの素……小さじ1と1/2
- ・塩……小さじ1/4
- ・しょうゆ……小さじ1
- ▲▲▲ B ▲▲▲

【作り方】
- ① 長ネギは小口切りにし、れんこんとしょうがは良く洗って皮ごとすりおろす。
- ② ボウルに鶏ひき肉とAを入れてこねながら、よく混ぜ合わせる。
- ③ 鍋にごま油を熱し長ネギをしんなりするまで炒めたら、れんこんを入れてさらに軽く炒めて、水を加える。
- ④ 沸騰してきたら、➁に鶏ひき肉をスプーンなどで一口大に丸めながら鍋に入れていく。
- ⑤ 鶏団子に火が通ったら、豆乳とBを加えてよく混ぜる。
- ⑥ 最後にしょうがを加えて、ひと煮たちさせたら出来上がり。

タンパク質豊富な鶏もも肉をふわふわでしっとりした肉団子にし、食欲そそる中華スープにしました。
スープに入れる豆乳は植物性タンパク質が豊富なことに加え、甘みとコクを生みだしてくれます。
加熱したれんこんには体を温める作用があり、しょうがと合わせることで寒い時期の朝にもピッタリのスープになりますので、ぜひ一度作ってみて下さい。